ミライのお仕事『注目企業へのインタビュー』企画。今回は、オークマ株式会社にインタビューしました。この記事では、転職を検討されている方に向けて、同社で働く魅力をご紹介します。
オークマは100年以上の歴史を持つ工作機械のリーディングカンパニーで、機械から電気系統まで一貫した開発・製造体制を持つことが特徴です。エンジニアのキャリア開発に特に力を入れており、大学院での学びの支援としてドクターコース支援制度や大学への研究者派遣制度、1年間の充実した実習期間を設けるなど、専門性を高められる環境が整っています。
また「ともに創る、ともに喜ぶ」というバリューのもと、チームワークを重視する社風も特徴的です。資格取得支援制度や階層別教育など、エンジニアとしての成長をサポートする体制も充実しています。
今回は、オークマ株式会社のエンジニアの育成やキャリアパス、社風などについて、CHRO(人事部門の最高責任者)の野﨑さんと、研究開発部の宇土さんにお話を聞かせていただきました。
更新履歴
2025年6月5日
- 同じトピックを紹介している「Qiita株式会社、ジークス株式会社、アストロサーブ株式会社、オプテックス株式会社、株式会社エーティーエルシステムズ」への内部リンクを追加しました。
2025年5月26日
- 採用・求人情報を追加しました
2025年5月21日
- 著者情報の変更を行いました
エンジニアのキャリアパス:専門性を深められる大学派遣のチャンスも
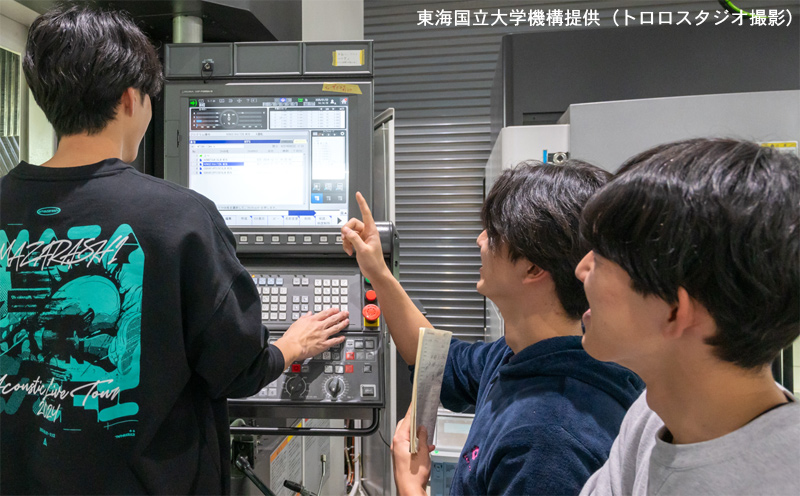
編集部
まずは、オークマでのエンジニアの育成方針について教えていただけますか?
野﨑さん
オークマでは単に製品を製造販売するだけでなく、技術者の専門性を高めていきたいという強い経営の意思があります。会社のコア技術を守り、発展させていくために、優秀な人材に成長のチャンスを与えるというのが核となる自社の考えです。
それを象徴するのが、大学への研究者派遣制度です。年間3〜4人程度の予算を設けて名古屋大学を中心とした企業派遣を行い、専門性の高い研究開発者、ドクターの育成を行っています。
編集部
宇土さんはまさに現在、オークマからの企業派遣で名古屋大学の助教として働いていらっしゃるんですよね。
宇土さん
はい。2018年にオークマに入社し研究開発に従事した後、2024年4月から名古屋大学で助教として働きながら研究を行っています。
私が所属しているオークマ工作機械工学寄附講座は、オークマの寄附により運営している研究室で、私自身もその研究室の卒業生です。オークマから派遣された助教にお世話になったという縁もありました。

▲2020年には名古屋大学東山キャンパスに、オークマの寄贈による「オークマ工作機械工学館」が完成
野﨑さん
宇土の場合は助教という立場での派遣ですが、企業派遣で純粋に大学院の博士課程に進むケースもあります。現社長の家城も入社後に大学院で学び、ドクター(博士号)を取得しています。
キャリア形成の上で本人が大学での学びを希望することが前提ですが、入社後にさらに研究を深められるチャンスがあることは求職者にとっても魅力的に感じてもらえることが多いですね。
編集部
企業と大学とで、研究の違いを感じる部分はありますか?
宇土さん
オークマでは各部署に専門性の高い人材が配置される分業体制を築いていますが、大学はそこまで棲み分けが明確ではない分、幅広い研究に触れられるのも魅力です。学生の研究に関わりながら、自分自身の知見を広げていける環境があります。
一方で、明確な目標設定と計画性を重視し、想定されるリスクや失敗要因も事前に予測して行う効率的な研究は、利益追求を行う企業ならではの強みです。大学と企業、どちらもそれぞれの良さがあり、双方を経験できることはエンジニアとしてありがたい環境です。
エンジニアとして幅広い知識を習得できる、1年間の手厚い実習制度

編集部
エンジニアとして入社後の教育体制についても教えてください。
宇土さん
オークマでは新卒入社の教育が手厚いのが特徴で、技術や技能について入社1年目を丸々実習期間として設けています。
最初の1か月は社会人としての基礎や工作機械の基礎知識を学ぶ集合教育があり、その後の11か月間は各部署をローテーションしながらOJTで業務を覚えていきます。実習を経て、最後の1か月くらいで本人の希望調査と上長の検討を踏まえて配属先が決定するという流れです。
編集部
1年間の実習期間というのは、他の企業と比べてもかなり珍しいのではないでしょうか。
野﨑さん
私も入社した当初は驚きました。ただし最近の新卒社員は「早く仕事で成果を出したい」という希望を持つ方も多く、価値観の変遷に合わせて職種によってもう少し早い段階での配属も実行しています。
ただ、やはり技術を必要とする専門性の高い職種はより慎重に適性を見極める必要もあるため、基礎教育のスピード感を早めつつ適材適所の配属を考慮しています。
編集部
製造業では1つの部署に配属されて専門性を高めていく会社も多いと思いますが、さまざまな部署を経験できる環境は、その後のキャリアにどのような影響を与えていますか?
宇土さん
私のときは、将来的に配属される可能性のある機械系部門の部署に加え、生産が特に忙しかったこともあり半年間は製造現場で業務支援を行いました。実際に部品に触れ、機械の仕組みや製造における課題、現場の考えを学べたことは、今の研究開発の仕事にも大変役立っています。
また、多くの部署を経験することで社内での関係づくりもできるため、仕事の円滑化という点でもメリットがあると思います。
実務だけじゃない、ビジネスパーソンとしての成長を見越した教育機会も充実

編集部
その他の教育機会としてはどのようなものがありますか?
野﨑さん
ロジカルシンキングや問題解決力といった、いわゆるポータブルスキルを養う階層別教育を若手のうちから導入しています。また今後は20代から50代まで幅広い年齢層に向けたキャリア教育も拡充しています。
実は過去の工作機械業界には、技術面の向上には力を入れるものの、広義の「人材育成」自体にあまり投資をしない傾向がありました。しかし会社の長期的な発展のためにも、人財教育は非常に重要です。キャリアの自律を促進するためにも、能力開発につながる配属後の教育体制を整えているところです。
編集部
福利厚生面での特徴的な制度はありますでしょうか。
野﨑さん
特筆すべきは資格手当制度です。120種類以上の資格が対象で、取得した資格に応じて月額最大2万円まで手当が支給されます。技術系のものからTOEICまで、対象となる資格の種類はさまざまです。
この制度には「社員に学ぶことへの関心を持ってほしい」という会社としての強い思いが込められています。資格取得を通じた自己啓発が、最終的に仕事のアウトプットにも良い影響を与えると考えています。
エンジニアの成長を支援する企業
オークマの社風:チームワークを大切に、助け合える環境

▲中央にいるのが野﨑さん。オークマアメリカの役員からプレゼントされたお揃いのシャツで笑顔を浮かべている
編集部
オークマの社風について、特徴的な点をご紹介いただけますか?
宇土さん
当社の「ともに創る、ともに喜ぶ」というバリューを体現する、困っていたら助け合える和やかな雰囲気が特徴的です。言い換えると、実力主義や競争意識ではなく、チームワークを大切にする社風であるといえます。
製品開発において他の部門の意見が必要になる場面も多いですが、相談すると丁寧にアドバイスしてくれる方が多く、私自身もたくさん助けられています。
編集部
野﨑さんは前職と比べて、カルチャーの違いを感じる点はありますか?
野﨑さん
前職では自身の成果を主張するのが当たり前の文化だったため、オークマの謙虚で優しい文化には良い意味でのギャップを感じました。
その背景には、当社が単一事業を展開しているということもあります。全社員が1つのバリューチェーンの中で協働していく必要があるからこそ、チームワークを大切にする文化が醸成されているのだと思います。
柔軟な働き方で技術を追求する企業
オークマから求職者へのメッセージ

▲2023年にはさいたま市にカフェ風の寛ぎ空間が特徴の営業拠点を新設
編集部
最後に、読者に向けてメッセージをお願いします。
宇土さん
当社は100年以上の歴史を持つ工作機械メーカーです。特徴的なのは、機械だけでなく、制御装置の開発から製造まで、社内で一貫して行える体制を持っていることです。多様な部門にいるプロフェッショナルとの協働機会は、エンジニアとしての成長にも大きく寄与すると思います。
さらにオークマでは、脱炭素やAIなど時代の流れを踏まえた新たな技術にも積極的に挑戦しています。100年以上の歴史がある中でも常に新しい課題や改善点を追求し続けられる、エンジニアとして非常にやりがいを感じられる環境です。
興味を持っていただけたのであれば、ぜひ応募していただければ嬉しいです。
野﨑さん
オークマでは、想像力豊かに新しい発想ができる人材を求めています。製造業では時として新しい発想を受け入れにくい面もありますが、オークマでは事業の成長のためにカルチャー改革を加速しています。ルール遵守を前提に、「こんなこともできる」「あんなこともやれるかも」という自由な発想で、可能性を広げていきたい方を歓迎しています。
一方で、「ともに創る、ともに喜ぶ」というバリューの通り、チームワークもとても大切です。自由な発想を持ちながら、相手をリスペクトでき誠実なコミュニケーションが取れる方に、ぜひ当社に来ていただきたいと考えています。
編集部
宇土さん、野﨑さん、本日はありがとうございました!
編集後記
オークマ株式会社の働き方のまとめ
| エンジニア育成 |
|
|---|---|
| 社風 |
|
| 技術的特徴 |
|
| 福利厚生 |
|
| 求める人物像 |
|
オークマ株式会社の採用・求人情報
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 主な募集職種 | 電情系・機械系 |
| 勤務地 | 愛知県丹羽郡大口町 |
| 想定年収 | 330万円〜1000万円 |
| 勤務時間 | 08:20~17:05(所定労働時間8時間) |
| 休日・休暇 | 休日:124日 ※内訳:土曜・日曜・夏季5日 その他:年末年始7.5日/GW9日/お盆5日※2023年度 有給休暇:有(~20日) ※4/1入社は入社時に14日付与 |
| 採用ページ | https://www.okuma-saiyou.jp/ |
※2025年5月現在(最新情報は企業のHPで必ずご確認ください)
| 企業名 | オークマ株式会社 |
|---|---|
| 公式ページ | https://www.okuma.co.jp |
| 本社所在地 | 愛知県丹羽郡大口町下小口五丁目25番地の1 |
| 業種 | メーカー(機械・電気)業界 |
| 事業内容 | NC工作機械(NC旋盤、複合加工機、マシニングセンタ、研削盤)、NC装置、FA製品、サーボモータ、その他、製造・販売 |
| 設立 | 1918年7月 |
| 従業員数 | 3,969名 |
| 資本金 | 18,000百万円 |



